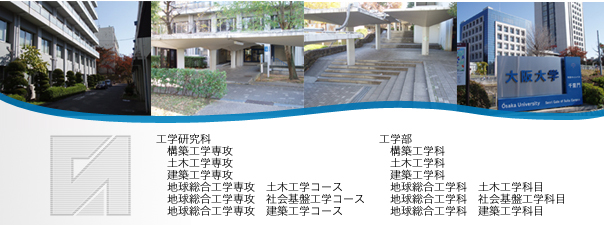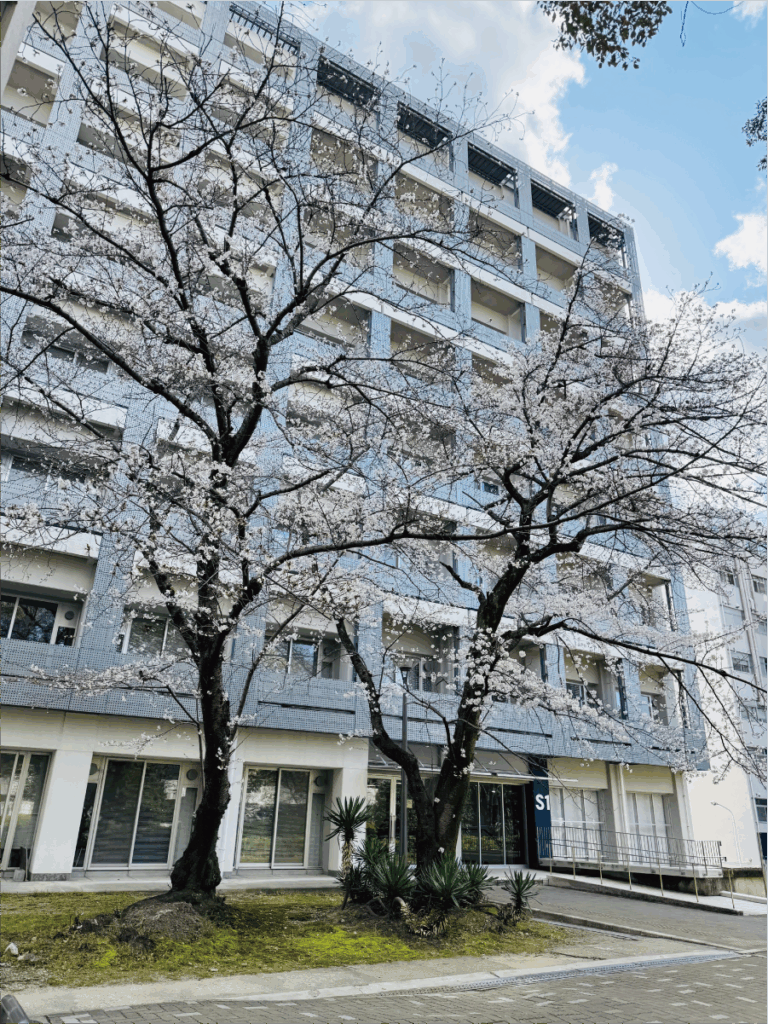建築工学科 1976年入学、1980年卒業の同期同窓会です。
我々は在学中から大変にコミュニケーションが良く、同期入学から同期卒業まで皆が「同期生」として、長く深く付き合っています。
皆68~9歳となり、いよいよ古希間近となりました。
健康や老いも気になるところですが、まだまだ楽しい人生を語り合います。
大阪にての開催ですが、東京の人も大歓迎です!
多くの人の参加を期待しています。
同窓会名:建八会 in大阪 2026
開催日時:2026年1月26日(月)
開催場所:中国菜 feve.(フェーヴ) (大阪市北区大淀中1-12-7,050-5600-8689)
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27105486/
参加対象者:1980年卒 建築工学科 同期生