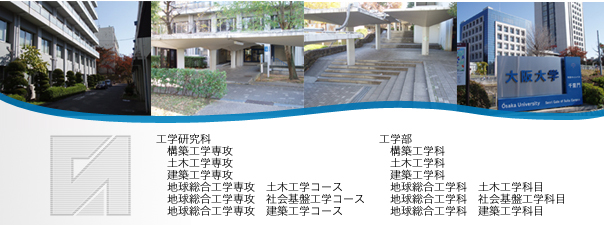構築会東京支部会員各位
会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
本年も総会・懇親会及び講演会を下記要領で開催します。またNOVARE見学会(定員10名)も企画し
ております。万障お繰り合わせの上ご出席下さいますようお願い申し上げます。
2025年7月22日
構築会東京支部 支部長 喜田 克英 (A-81)
副支部長 黒川 純一良(C-84)
記
- 開催日:2025年9月29日(月)17:30~20:45
- 場 所: 総会・講演会:NOVARE forum※(清水建設施設)https://www.shimz.co.jp/novare/
※入場時QRコード必要(出欠確認後、別途メールにて送付)
懇親会:東京イーストサイドホテル櫂会2F メインダイニング「アンサンブル」
- 総会・講演会:17:30~18:45(17:00受付開始)
タイトル「インフラEBPM研究の社会実装」
大学院工学研究科地球総合工学専攻 社会基盤工学部門長 貝戸 清之 教授
タイトル「高力ボルト関連研究の近況」
大学院工学研究科地球総合工学専攻 建築工学部門長 桑原 進 教授
- 懇親会:19:00~20:45
会 費:2013年3月学部卒業 以前の方 8,000円
2014年3月学部卒業 以降の方 6,000円
新入会員(2025年3月卒業の方)無 料
詳細は下記ファイルを参照下さい。
https://kouchikukai.jp/wp/wp-content/uploads/dc3bcee1f95f0076b787cfb2c6228c3d.pdf
ご出欠を8月25日(月)までに下記フォームよりご回答ください。
https://forms.office.com/r/j6r9yKLE6U
フォームにアクセスできない方は、①氏名、②卒業年 ③連絡先 ④出欠をお知らせください。
問合せ先:構築会東京支部 幹事長 清水建設 粕本 修広(A-97) kasumoto@shimz.co.jp
以上